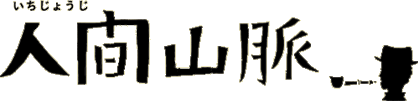恵文社一乗寺店ウェブサイト
連載コンテンツ
「いちじょうじ人間山脈」
題字:関美穂子
第三十五回
伊藤聡信さん(陶芸家)
2012年5月25日取材 インタビュー/原稿:田川怜奈

個性豊かな作家さん、アーティスト、取引先の皆さんと毎日のように関わりながら成り立っている当店。そんな人々を探れば自ずと店の輪郭までもが浮かび上がるのではないかということで、スタートしました連載「一乗寺人間山脈」。今回は先月、生活館ミニギャラリーでも展示頂いた伊藤聡信さん。白磁や色絵の器など、当店でも大変人気のある作家さんです。今回はお持ち頂いた書籍を中心に、お話を伺いました。
― ご自身の座右の書ということで、『芸術新潮』(2001年4月号特集 4人の骨董商*1) をお持ち頂いたのですが、どういった部分に影響をうけられたのでしょうか?
この特集を読んだら、あまりにも坂田さん、大嶌さんが格好良くて。お店にも伺ったら置いているものも素敵だったし。
この本から影響を受けて白磁が良いなと思った。白磁って使いやすいでしょ、水吸い込まないし。それで(大嶌さんに見てもらおうと思って)白磁の小さいくみ出しを作って、大島さんに電話かけたの。そしたら「ものは見ないけど、会っても良い」って。
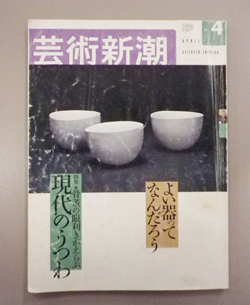
『芸術新潮 2001年4月号』( 新潮社 刊 )
― (笑)ものは見ないけど・・・。
決死の思いで会いに行って、それで1、2時間話ししてたら見ても良いよって。やった!と思って見せたら「良いけど下手だね」って(笑)。かっちり作ったはずなんだけど高台の形が歪んでて。そのあと作り直してひと月後にまた見せたら上手くなったねって言ってくれた。それで来年の2月から展示やろうって話になって。
― とんとん拍子ですね。大嶌さんは本当にお師匠みたいな存在なんですね。
うん、そう。輪花皿とかこんにゃく印判やらないかって言ったの大嶌さんだから。
― ええっ!そうなんですか。
やってみますって言って作ったら、これ良いねって大嶌さんに言ってもらえて。それから、一緒に仕事をやっていこうって話に。値段も一緒に決めたし。あと、色絵なんかも大嶌さんの店に行ったら(ヒントとなる商品が)あったから。大嶌さんのお店(魯山)の常設を見に行くと、必ず(創作の)ヒントがあるの。大嶌さんがどのへんにアンテナを張り巡らしているかっていうのがわかる。ジャンクなものもあるしね。これとか(壁に立て掛けられたトタン板を指す)。今回のスペイン皿も、前に大嶌さんのお店に行ったらあった。大嶌さんは日本の食器ばかり扱っていると思っていたけど、そんなスペインのものもあるんだなって。これもありなのかなーって。
― でもそうだとしても、それを意識させない「伊藤さんの」作品になっていますよね。
だから大嶌さんはいつも「買ったものを見てそのまま作るな」って言うね。無名なものでも大きさ変えたり素材を変えたり、元を辿って自分なりにアレンジするように。いろいろアプローチの仕方があるよね。だから新しいこともしつつ、自分の定番のものも良くしていきたい。ただ、自分の中の文脈がわかるようにはしていたいよね。白磁があって印判があって、その上に色をのせてとか。自分で展開を把握していかないとバラバラになるから、釉薬とか土は共通のものを使って、焼き方や組み合わせを変えたりしてる。
― 伊藤さんはご自宅ではご自身の器で召し上がったりされますか。展示会のDMは、この器をぜひ家でも使いたいと思わせる素敵な写真でしたが。
うん。主に白磁を使ってる。うちのかみさんが白磁大好きで。色絵の器はほぼ使ってないかな・・・でも(食卓における器の)バランスが大切だよね。ぜんぶ同じような器で揃えるのではなく、古い器があっても良い。 展示会もバランスで、売れるからって全部色絵にするのではなくいろいろ並べるし。でも売れるものが良いとは限らないでしょ。ずっと売れ続ける訳ないから。だから色絵ばかり作ってるのじゃなくて、白磁も仕込んで絶えず時代にあわせて微調整しながらやってる。商売もそうだけどね。好きなもの、売れるものいろいろあるしね。
展示会搬入後のお疲れのところ、細やかにお話頂きました。伊藤さんが「ふだんづかいの器」を強く意識されていることを知り、すんなりと納得できたのは、それがそのまま作品に反映されているからでしょう。本に掲載の器を指しながら「アパート暮らしの食卓にこれはあわない」ときっぱりおっしゃっていたのが印象的でした。自分の内側に入っていくだけではなく、周りのものや人とキャッチボールしながら取捨選択して制作されているのが、広い視野の秘訣なのだと思います。お話に出た「魯山」では8月末に8回目の個展をされるそう。お近くにお住まいの方は、ぜひお立ち寄りください。
*1浦上満 (日本橋・浦上蒼穹堂主人)、大嶌文彦(西荻窪・魯山主人)・坂田和實(目白・古道具坂田主人)・柳孝(京都・古美術柳主人)